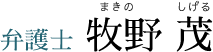遺産分割協議で相続人が行方不明の場合の対処法とは?ケース別に解説します
相続人の中に行方不明者がいる場合、相続手続きを進めることが難しくなります。
行方不明者にも法律で定められた相続権があるため、状況に応じて不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てなど、適切な対応が必要です。
本記事では、行方不明の相続人がいる場合の対処方法について解説します。
相続権は行方不明の相続人にも認められる
相続人とは、被相続人の財産を引き継ぐ立場にあるひとのことです。
相続人の資格は民法によって厳密に定められており、任意で変更することは認められていません。
長年の関係が途絶えていた場合でも、法律で定められた相続人には相続権があります。
相続手続きを進める際、行方不明の相続人がいることも珍しくありません。
そのような状況であっても、行方不明の相続人の相続権を無視して相続手続きを行うことができないケースがあります。
遺産分割協議には行方不明の相続人も含める必要がある
そのケースが、遺産の分け方を遺産分割協議で決める場合です。
相続手続きでは、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合って決めます。
遺産分割の話し合いは、一部の相続人だけで進めることはできません。
行方不明の相続人がいる場合は、遺産分割の手続きを開始できない状態となります。
そのため、行方不明者に連絡を試みることが必要です。
所在が判明しない場合には、法的な代理人を選任して遺産分割の話し合いを進める必要があります。
遺言書があれば遺産分割協議は不要になる
遺言書が用意されている場合は、民法の定める相続の規定よりも遺言の内容が優先されます。
遺言書によって財産の承継者が指定されているため、相続人全員での話し合いは不要です。
行方不明の相続人がいる場合、遺言書で指定された相続人のみで相続手続きを進めることができます。
行方不明の状況によって異なる対応方法が必要
行方不明の相続人への対処方法は、その状況によって対応方法が異なります。
ケースごとに、適切な対応方法を確認していきましょう。
相続人の生存は確認できるが住所がわからない場合
相続人が、連絡手段として電話やメール、SNSを活用しており、生存は確認できている場合があります。
時折、親族に連絡があるというような相続人は、住所登録地の確認が優先的な対応となります。
住所登録地を調べるには、戸籍の附票の取得が有効な手段です。
戸籍の附票は、戸籍が置かれている市区町村役場の市民課で取得することができます。
相続人が見つからない場合は不在者財産管理人制度の利用を検討
行方不明の相続人の住所がわかっても、実際には居住していない場合や、住所の特定自体が困難なケースがあります。
このように、相続人が消息不明や生存が確認できない場合、裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることで解決することが可能です。
不在者財産管理人は、行方不明の相続人の代理人として遺産分割を進める権限を持ちます。
不在者財産管理人を選出方法
不在者財産管理人の選任には、行方不明者の配偶者や他の相続人、債権者など利害関係がある人物が申立てを行う必要があります。
手続きに必要な書類は家庭裁判所で確認しておきましょう。
確実に手続きを完了するために、事前に弁護士などの専門家や管轄の家庭裁判所へ相談することがおすすめです。
どんな人物が不在者財産管理人に選任されるのか
被相続人の親族のうち、遺産分割に利害関係を持たない人物が不在者財産管理人になるケースが一般的です。
適任者が見つからない場合、家庭裁判所が弁護士や認定司法書士といった法律の専門家から選任します。
家庭裁判所から正式な許可を得た不在者財産管理人は、遺産分割協議に参加し財産管理を行うことが可能です。
失踪宣告の制度について
失踪宣告は、生死がわからないひとを法律上で死亡したとみなすための制度です。
家庭裁判所への申立てを経て、正式に失踪宣告を受けることができます。
失踪宣告が認められた場合、その人物は法律上で死亡したものとして扱われるため、遺産分割協議を対象者不在のまま進行することが可能です。
普通失踪
普通失踪とは、家出などにより住所地を離れ、簡単には戻る見込みがない状態を指します。生死が不明となった最後の日から7年が経過した時点で、家庭裁判所へ失踪宣告の申立てが可能です。
家庭裁判所から失踪宣告が出された場合、その行方不明者は7年が経過した日に死亡したとみなされるため、遺産分割協議を行う際に本人の参加は必要なくなります。
普通失踪の制度は、民法第30条第1項に規定されています。
特別失踪
特別失踪とは、山岳遭難や海難事故など、生命が危険にさらされる状況で行方不明となったケースです。
危険な状態が収束してから1年が経過すれば、家庭裁判所へ失踪宣告の申立てができます。
普通失踪と比べて申立てまでの期間が大幅に短縮されているのが特徴です。
家庭裁判所から失踪宣告が出されると、危険な状況が去った時点で死亡したとみなされるため、遺産分割協議での本人の参加は不要となります。
特別失踪の制度は、民法第30条第2項に規定されています。
まとめ
相続人が行方不明の場合でも、その相続権は法律で保護されているため、遺産分割協議から除くことはできません。
ただし、遺言書がある場合は、行方不明の相続人がいても手続きを進めることが可能です。
遺産分割協議を進めるためには、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てなど、状況に応じた適切な法的手続きが必要となります。
相続手続きを円滑に進めるためにも、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
-
裁判員制度におけるメ...
裁判員制度は日本の司法システムを支える大切な仕組みとして根付いてきました。一般市民が、裁判官と協力しながら刑事裁判に携わり、被告人への判断を下す制度として、裁判員制度は機能しています。 本記事では、市民感覚を大切にし、透 […]

-
裁判員制度とは
裁判員制度とは、国民が裁判官とともに刑事裁判に参加し、被告人が有罪であるか否か、有罪であるとしてどのような刑罰を課すかを判断するものです。殺人事件や放火事件など、国民の関心が高い重大犯罪について制度の対象となっています。 […]

-
相続トラブルを弁護士...
遺産相続では、相続人同士の話し合いがうまくいかずトラブルに発展するケースが少なくありません。相続問題を円滑に解決するためには、弁護士をはじめとする専門家への相談が効果的です。本記事では、弁護士に早めに相談するメリットと、 […]

-
遺言書における3つの...
一般で作成される遺言書には、3つの種類があります。遺言書を円滑な相続手続きに役立てるためには、各種類の違いを理解したうえで、自分が重視するポイントや、作成・保管状況に合うものを選ぶことが大切です。今回は、遺言書における3 […]

-
寄与分と特別受益とは...
相続における寄与分と特別受益は、相続人間の公平な財産分配を実現するための重要な制度です。相続人それぞれの被相続人への貢献度や、生前に受けた財産を適切に評価することで、納得のいく相続が可能となります。本記事では、寄与分と特 […]

-
賃料の減額交渉と減額...
賃貸物件の賃料が高額だと感じる場合、オーナーに対して減額交渉することが可能です。減額してほしい旨を相談するだけでなく、条件によっては法的に減額請求できる可能性もあります。この記事では、賃料の減額交渉と減額請求権を行使でき […]

よく検索されるキーワード
弁護士紹介
昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
-
- 第二東京弁護士会(17922)
- 第二東京弁護士会裁判員センター
- 日弁連刑事弁護センター幹事
- 著書
-
- 裁判員裁判のいま(成文堂)
- 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
- 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
- 裁判員制度の10年(日本評論社)
事務所概要
| 名称 | フェアネス法律事務所 弁護士 牧野 茂 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル10階 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:03-3500-5330 / FAX:03-3500-5331 |
| 対応時間 | 平日:9:00~18:00 ※時間外も対応しております(要予約) |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※対応しております(要予約) |
| アクセス |
地下鉄銀座線虎ノ門駅下車(7番出口より徒歩1分) 丸ノ内線・日比谷線・千代田線 霞が関駅下車 A12出口より 徒歩3分 |