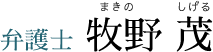裁判員裁判はどんなときに行われる?流れや手続きについて詳しく解説
2009年にスタートした裁判員裁判制度は、重大な刑事事件を裁判官と一般市民が一緒に審理します。
この制度は、より身近で信頼される司法の実現を目指すものです。
本記事では、裁判員の選び方から具体的な裁判の進め方など、制度の基本的な仕組みについて解説します。
裁判員裁判の基本的な仕組み
裁判員裁判制度は、一般市民が重要な刑事裁判の判決に携わる仕組みです。
一般市民の中から無作為に選ばれた裁判員が、法律の専門家である裁判官と一緒に審理を進めていきます。
被告人の罪を決定し、適切な刑罰を判断する役割を担うことで、国民目線の公平で信頼される裁判を実現することが可能です。
裁判員裁判の対象となる事件
裁判員裁判の対象となる事件は、法律で定められた特定の重大事案に限られています。
法律で定められた対象事件は、大きく2種類に分けられます。
ひとつは、死刑・無期刑に関連する重大事件と被害者が命を落とした故意の犯罪です。
裁判員が審理に加わる具体的な事案には、殺人による生命を奪う犯罪や、強盗致死傷のような凶悪犯罪が含まれます。
次に、強制性交等致死傷、現住建造物等放火なども重要な対象事件です。
加えて、傷害致死、保護責任者遺棄致死、危険運転致死なども裁判員裁判で扱われる重大事件として定められています。
通常裁判と裁判員裁判の進め方の違い
裁判員裁判は、一般市民の方々の日常生活への負担を考慮した短期集中型の審理を実施しています。
普通の裁判では審理の間に1か月ほどの間を空けることが多いですが、裁判員裁判では連続的に審理を行うのが一般的です。
公判前整理手続という、裁判官や検察官、弁護人が集まり、争いとなる点や必要な証拠を細かく整理する事前準備が行われ、審理が効率的に進む工夫がされています。
この充実した準備作業によって、裁判員が参加する本審理は連日開廷され、スムーズに進行することができるのです。
裁判員の選任手続きについて
裁判員裁判では、ひとつの事件において6人の市民が裁判員として加わることが定められています。
選出対象は20歳以上の選挙権を有する日本国民とされていて、公平な抽選で選ばれます。
完全な無作為抽選で決定されるため、誰でも裁判員になる可能性があり、特定の職業や立場による優遇はありません。
裁判員候補者名簿が作成される
裁判員候補者の選定は、各地方裁判所が秋頃から翌年の準備を進め、選挙管理委員会による公平な抽選で、選挙人名簿の中から候補者名簿が作られます。
候補者へ通知し調査手続きを実施する
裁判員候補者への通知は前年の11月頃に送られます。
候補者となった場合、自衛官や警察官などの就任できない職業についているか、健康状態に問題がないかを確認する調査票に回答を記載し返送しなくてはいけません。
各事件ごとにくじ引きによって候補者選定を実施する
裁判員候補者名簿に登録された方々の中から、事件ごとに公平な抽選が行われ、ひとつの事件ごとに、6人の裁判員が最終的に選任されるのです。
選任手続期日の通知と質問票の送付する
裁判が始まる6週間前までに、選出された裁判員候補者に呼出状と質問票が届きます。
公平な裁判運営のため、約70人の補充裁判員候補者も選出されます。
補充裁判員候補者は、病気などで急な欠員が出た際に選ばれる重要な役割を担う存在です。
選任手続当日の流れ
裁判員候補者は、裁判所から指定された日時に選任手続に参加しなくてはいけません。
裁判長は公平な判断ができるかの確認や、辞退を希望する理由の有無などの質問を行います。
最終的に6人の裁判員を選任する
選任手続が終わると、各事件につき、6人の裁判員が正式に選ばれます。
スムーズな裁判運営のため補充裁判員が追加で選任される場合もあることを覚えておきましょう。
裁判員裁判の具体的な流れ
裁判員裁判では、最初に裁判官と検察官、弁護人が公判前整理手続を進め、それを土台として、裁判員が審理に参加することになります。
最終的には、裁判員と裁判官による慎重な評議を経て、適切な判決が導き出されていくのです。
公判前整理手続の実施
裁判員の公判への参加に向けて、公判前整理手続が大切な役割を果たします。
裁判官たちは綿密な審理計画を立て、裁判員の負担軽減に努めます。
審理の論点を明らかにし、証拠の選別を行い、具体的な日程を組み立てていく作業が進められるのです。
公判期日の到来
裁判員は公判開始日から審理に参加します。
事前の準備段階である公判前整理手続に関わることはありません。
複雑な事案を除いて、多くの審理は1週間以内に終わりを迎えます。
法廷での審理は、最初に冒頭手続を行い、その後は証拠調べ、検察による論告・求刑、弁護側の最終弁論と進められていくのが一般的です。
評議の実施
評議室では、裁判員と裁判官による非公開の討議が慎重に進められます。
判決を決める際には、裁判官と裁判員が平等な1票を持っています。
有罪の判断には、裁判官と裁判員からそれぞれ1名以上を含めた過半数の賛成が必要です。
量刑についての意見が分かれた場合は、裁判官と裁判員双方から1名以上を含む過半数の中で、被告人に最も有利な意見が採用される仕組みとなっています。
判決の宣告
裁判所は評議で導き出された内容をもとに、法廷で判決を宣告します。
被告人や検察官が判決内容に不服がある場合は、2週間以内に控訴する権利が認められていますが、控訴審での裁判には裁判員が加わることはありません。
まとめ
裁判員裁判制度は、一般市民が重大な刑事裁判に参加することで、より開かれた司法を実現する仕組みです。
裁判ごとに無作為で選ばれた6名の裁判員が、裁判官とともに被告人の罪の有無や刑罰を決定します。
短期集中型で実施されるため、事前の準備を入念に行い、公平かつ効率的な審理が行われます。
この制度により、国民の視点を反映した、より身近な司法制度の実現を目指しているのです。
当事務所が提供する基礎知識
-
遺産分割協議後のやり...
遺産分割協議とは、文字通り被相続人の遺産を共同相続人の間でどうやって分割するかについての話し合いです。被相続人の遺言がない場合や何かしらの書き漏れで遺言の効力を有さなくなった場合に行われます。この遺産分割協議が無効になる […]

-
裁判員が行う仕事と役...
裁判員は刑事裁判に参加します。刑事事件の審理に参加し、証人や被告人に対する質問を行います。また、証拠の取調べも行います。審理を終えたあとは評議を行います。審理を通して知った事実や証拠に基づいて、被告人が無罪であるか有罪で […]

-
欠陥住宅
新築の住宅に雨漏りが生じたり、不自然な隙間が見つかったりして、欠陥住宅であることが判明した場合、一定の場合では法的な救済を得ることができます。見つかった欠陥をそのまま放置するのではなく、建築業者や不動産業者に報告すること […]

-
裁判員制度におけるメ...
裁判員制度は日本の司法システムを支える大切な仕組みとして根付いてきました。一般市民が、裁判官と協力しながら刑事裁判に携わり、被告人への判断を下す制度として、裁判員制度は機能しています。 本記事では、市民感覚を大切にし、透 […]

-
家賃滞納が起こった際...
不動産オーナーにとって、入居者とのトラブルで最も頼りになるのが「弁護士」です。入居者(賃借人)の家賃滞納は、オーナーが抱える大きなトラブルの1つであり、迅速な対応と注意が求められます。本記事では、家賃滞納が起こった際の対 […]

-
不動産売買契約はキャ...
不動産売買契約のキャンセルは、さまざまな状況で認められています。手付金の放棄による解除から、契約不適合による解除まで、複数の選択肢があります。本記事では、契約のキャンセルの可否や、キャンセルが可能となる具体的なケースなど […]

よく検索されるキーワード
弁護士紹介
昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
-
- 第二東京弁護士会(17922)
- 第二東京弁護士会裁判員センター
- 日弁連刑事弁護センター幹事
- 著書
-
- 裁判員裁判のいま(成文堂)
- 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
- 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
- 裁判員制度の10年(日本評論社)
事務所概要
| 名称 | フェアネス法律事務所 弁護士 牧野 茂 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル10階 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:050-3173-8287 / FAX:03-3500-5331 |
| 対応時間 | 平日:9:00~18:00 ※時間外も対応しております(要予約) |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※対応しております(要予約) |
| アクセス |
地下鉄銀座線虎ノ門駅下車(7番出口より徒歩1分) 丸ノ内線・日比谷線・千代田線 霞が関駅下車 A12出口より 徒歩3分 |