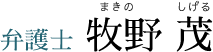家賃滞納が起こった際にすべきこと
不動産オーナーにとって、入居者とのトラブルで最も頼りになるのが「弁護士」です。
入居者(賃借人)の家賃滞納は、オーナーが抱える大きなトラブルの1つであり、迅速な対応と注意が求められます。
本記事では、家賃滞納が起こった際の対応方法について解説いたします。
家賃滞納によるオーナーが抱えるリスク
家賃滞納による大きなリスクは以下の2つが挙げられます。
すぐに退去要請できるわけではない
家賃の滞納が続けば、契約解除を請求するだけと思われるかもしれませんが、入居者の権利は強く保護されています。
退去を請求するには最低3か月以上の滞納歴が必要となり、要件を満たして初めて訴訟を提起し、退去請求ができます。
退去請求に費用と時間を要する
退去請求から退去完了までには多くの期間と費用が必要となります。
入居者に差し押さえられるような財産がない場合、家賃滞納が1件発生するだけで、滞納家賃と裁判期間中の数か月間の家賃収入が得られない上に裁判費用を負担することになる可能性があります。
家賃滞納が起こった際にオーナーがすべきこと
家賃滞納が起こった際には、一般的にオーナーは以下の手順で対応を進めます。
入居者に口頭、電話、書面で支払いの督促
家賃の未払いが確認されたら、すぐに入居者へ支払いの督促を行いましょう。
まずは口頭または電話で連絡し、連絡が取れない場合は書面で督促します。
家賃保証会社または連帯保証人に連絡
入居者への督促で支払いが確認できない場合は、家賃保証会社または連帯保証人に連絡します。
家賃保証会社を利用している場合は保証会社へ連絡すると、家賃保証会社が家賃の立て替えと入居者への家賃支払いの督促を行います。
一方、連帯保証人は入居者に親しい人物である場合が多いです。
そのため連帯保証人に連絡すると、連帯保証人から入居者へ連絡が行く場合がほとんどであるため、入居者からの支払いが期待できます。
入居者へ内容証明郵便を送る
家賃滞納が2か月続き、連帯保証人からも家賃が支払われない場合、入居者へ内容証明郵便での督促を行います。
内容証明郵便は、郵便局が督促の事実を証明してくれるため、退去請求の裁判となった際の重要な資料となります。
合わせて、連帯保証人にも同内容の内容証明郵便を送付しましょう。
任意での明け渡しを請求する
内容証明郵便での督促後にも家賃滞納が続く場合、家賃の回収は一旦諦めて、任意での明け渡しを検討する段階です。
明け渡し訴訟にまで持ち込むと、更に6か月家賃収入が得られない状況が続くため、任意での明け渡しに応じてもらえるか交渉します。
入居者の権利が強く保護されているため、強引な支払い・退去の要求はしないように注意が必要です。
法的な手続きを取る
入居者が任意での明け渡し要求にも応じない場合、法的手段の行使が必要です。
法的手段には3つの手段があり、状況に合わせて手段を選択します。
続いてそれぞれの法的手段について解説します。
法的手続きの流れ
法定手続きは以下の3つの手続きから選択可能です。
- 支払督促
- 少額訴訟
- 明け渡し訴訟
それぞれ詳しく解説します。
支払督促
支払い督促はオーナーに代わって、裁判所が滞納者に対して滞納家賃の督促状を送付する方法です。
裁判は起こさないため、時間や費用を抑えながら、督促に応じない場合は給与・財産の差し押さえまでできるメリットがあります。
しかし、支払い督促は金銭支払いのみ対象のため、退去させることはできず、滞納者に支払い能力がない場合には支払い督促に効果はありません。
少額訴訟
少額訴訟は名前の通り、60万円以下の金銭支払いを請求できる手続きです。
1度の審理ですぐの判決が出るため、時間がかからないことが大きなメリットで、確実に勝訴できるだけの証拠を揃えられている状況のおいて、有効な手段です。
しかし、請求できるのは金銭支払いのみのため、退去要求はできず、和解の検討にも時間がかけられないため、滞納者からの分割支払い交渉にもすぐに判断し対応する必要があります。
明け渡し訴訟
滞納者に支払う意思が見られない、支払い能力がない場合の最終手段が、強制退去を求める明け渡し訴訟です。
支払い督促や少額訴訟と違い、退去まで請求できますが、期間が6か月ほどかかり、訴訟費用として30~50万円近くかかります。
また、明け渡しが認められるには目安として、以下の要件が必要とされています。
- 最低でも3か月以上の滞納
- 入居者に支払いの意思が見られない
- オーナーと入居者との信頼関係が破綻している
対応時の注意点
家賃の滞納が発生した際、家賃の支払い、または任意で退去をしてほしいと思った時にでも、以下の行為は行ってはいけません。
- 早朝・深夜の電話
- 入居者の学校・職場への連絡
- 家賃滞納がわかる張り紙の掲示
- 連帯保証人以外への督促
- 鍵の交換
- 無断入室と物の撤去
上記は入居者との余計なトラブルを増やす原因となるため、絶対に避けましょう。
まとめ
家賃滞納は家賃収入が止まるうえに、新たな入居も募集できず、空き家以下の状況であるため、早急に対処が必要です。
しかし、対応を誤れば、トラブルを増やす可能性もあるため、対応方法の検討から手続きには、入居者トラブルに強い、弁護士への相談がおすすめです。
当事務所が提供する基礎知識
-
不動産を売却時に注意...
不動産の売却は、多くの方にとって人生における大きな決断となります。適切な売却方法の選択や、取引を円滑に進めるためのポイントを知っておくことで、後悔のない取引が実現可能です。本記事では、住宅売却の具体的な方法と、契約から引 […]

-
不動産売買契約はキャ...
不動産売買契約のキャンセルは、さまざまな状況で認められています。手付金の放棄による解除から、契約不適合による解除まで、複数の選択肢があります。本記事では、契約のキャンセルの可否や、キャンセルが可能となる具体的なケースなど […]

-
成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などを理由に判断能力が不十分となった方々は、ご自身で契約を結ぶことや財産を管理することが難しく、ご自身に不利益な契約を騙されて締結してしまったり、財産管理を誤ってしまったりして、不利益を被るおそ […]

-
家賃滞納が起こった際...
不動産オーナーにとって、入居者とのトラブルで最も頼りになるのが「弁護士」です。入居者(賃借人)の家賃滞納は、オーナーが抱える大きなトラブルの1つであり、迅速な対応と注意が求められます。本記事では、家賃滞納が起こった際の対 […]

-
フランチャイズ紛争
フランチャイズとは、事業者同士の契約関係の一種を指します。指導や援助を行う立場の事業者を「フランチャイザー」といい、その下に事業を行っていく立場の事業者を「フランチャイジー」といいます。具体的なフランチャイズの内容として […]

-
受遺者とは何?相続の...
遺言書によって財産を受け取る権利を持つのが「受遺者」です。遺産を受け取るひとは「特定受遺者」または「包括受遺者」のいずれかに分類されます。両者の間では、遺産に関する法的な権利や責任の範囲が大きく違うので注意しましょう。本 […]

よく検索されるキーワード
弁護士紹介
昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
-
- 第二東京弁護士会(17922)
- 第二東京弁護士会裁判員センター
- 日弁連刑事弁護センター幹事
- 著書
-
- 裁判員裁判のいま(成文堂)
- 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
- 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
- 裁判員制度の10年(日本評論社)
事務所概要
| 名称 | フェアネス法律事務所 弁護士 牧野 茂 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル10階 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:050-3173-8287 / FAX:03-3500-5331 |
| 対応時間 | 平日:9:00~18:00 ※時間外も対応しております(要予約) |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※対応しております(要予約) |
| アクセス |
地下鉄銀座線虎ノ門駅下車(7番出口より徒歩1分) 丸ノ内線・日比谷線・千代田線 霞が関駅下車 A12出口より 徒歩3分 |