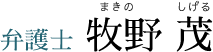相続人の1人に特別受益があったときの遺産分割協議の進め方とは?
相続において、特別受益の問題は避けて通れない重要なテーマです。
特別受益は、被相続人から生前に贈与を受けた財産が、相続時に計算の対象となり、他の相続人との公平な分配を実現するための仕組みとして機能します。
本記事では、特別受益の基本的な内容や、特別受益がある場合の遺産分割協議の流れ、注意点までを解説します。
特別受益とは何か?
特別受益は、相続人の中で一部のひとだけが被相続人から生前に受け取った財産のことです。
受け取った利益が特別受益に該当し、相続人が複数存在する場合に問題となります。
特別受益には3種類ある
特別受益は、「生前贈与」「遺贈」「死因贈与」の3種類があります。
以下でそれぞれみていきましょう。
生前贈与
生前贈与のうち、特別受益として扱われるのは婚姻・養子縁組・生計の資本に関する贈与です。
ただし、すべての生前贈与が特別受益になるわけではありません。
相続財産の前払いとみなせるかどうかという基準に基づいて、その贈与が特別受益に該当するか判断されます。
遺贈
遺言書の中で相続人に対して「特定の財産を譲渡する」と定められた贈与を遺贈といいます。
相続人が遺言書によって受け取る財産は、特別受益の対象です。
死因贈与
死因贈与は、贈与者が生前、「自身の死亡後に財産を譲渡する」という条件付きの契約を結ぶものです。
贈与者と受贈者の合意があれば死因贈与が成立し、受贈者が相続人である場合は特別受益として扱われます。
なぜ特別受益は相続トラブルを引き起こすとされているのか
特別受益がある場合の相続は、深刻な争いに発展するリスクが高いとされています。
それは、特別受益の金額や事実関係を巡って相続人同士の主張が食い違うケースが多く発生するからです。
トラブルの種類 | 具体的な内容 | 問題点 |
|---|---|---|
贈与事実の否認 | 特別受益者が贈与を受けた事実自体を認めない | 証拠の有無が争点となる |
金額の不明確さ | 贈与額の記録や証拠が残されていない | 正確な金額の特定が困難 |
認識の相違 | 特別受益者と他の相続人で金額の認識が異なる | 合意形成が極めて難しい |
このような状況は一度トラブルとなると解決までに長期間を要し、相続人同士の関係悪化を招く可能性が高くなります。
特別受益があった場合の遺産分割協議の進め方
特別受益があると考えられる場合、以下の手順で遺産分割協議を進めていくことになります。
遺産分割協議で特別受益の持ち戻しを主張する
特別受益の持ち戻しとは、特別受益の対象となった財産を相続財産へ加算することです。
相続財産の分割は遺産分割協議からスタートします。
特別受益の主張はこの遺産分割協議の場で行うことが最も適切な方法です。
具体的な証拠を用意した上で、関係者全員に特別受益の内容を説明すると、話し合いがスムーズに進みやすくなります。
遺産分割調停を利用して解決をはかる
遺産分割協議では相続人全員の同意が必須です。
特別受益の存在を認めない相続人がいる場合、家庭裁判所での遺産分割調停へと進むことになります。
遺産分割調停は、以下のようなステップで進めます。
- 調停の申立て:家庭裁判所に必要書類を提出し、正式に調停手続きを開始する。
この段階で証拠資料の準備が重要。 - 調停委員による仲介:調停委員が中立的な立場から双方の主張を聞き、解決に向けた助言を行う。
専門的な知見に基づく提案が期待できる。 - 話し合いの実施:調停委員の進行のもと、相続人同士が建設的な議論を行う。
双方の意見を丁寧に確認しながら合意点を探る。
ただし、調停はあくまで話し合いによる解決を目指す制度です。
相続人の対立が強い場合は、調停不成立となる可能性もあるので注意が必要です。
調停不成立となったら遺産分割審判による遺産分割を行う
遺産分割の調停がまとまらなかった場合、遺産分割審判の手続きへと自動的に進みます。
裁判所は、関係者が提出した資料や証拠を十分に検討したうえで、遺産分割の判断を下します。
相手方が特別受益の存在を否定する主張をしたとしても、客観的な証拠があれば、遺産分割の際に特別受益が認定されることになるでしょう。
特別受益の注意点
特別受益があったと考えられる場合に、注意すべきポイントがいくつか存在します。
以下で、具体的なポイントについて解説します。
特別受益に消滅時効はない
特別受益には時効制度が適用されません。
生前贈与が行われてから何十年もの時間が経過したとしても、特別受益として認定される可能性が残ります。
たとえば、20年以上前の住宅購入資金の援助も、他の相続人から申し立てがあれば、特別受益と認められる可能性があります。
遺留分計算での特別受益は相続開始から10年以内が対象となる
遺留分の計算に含められる特別受益は、相続開始時から遡って10年以内のものです。
たとえば、被相続人が亡くなる5年前の贈与は計算対象になりますが、12年前の贈与については、遺留分計算の対象外となります。
特別受益の主張には証拠資料が不可欠
特別受益の認定には、贈与の事実を証明する具体的な証拠が必要です。
贈与を受けた相続人が事実を認めないケースが多いため、他の相続人が特別受益を主張する際には、贈与の証拠を用意しておく必要があります。
まとめ
特別受益とは、相続人が被相続人から生前に受けた財産のことで、生前贈与・遺贈・死因贈与の3種類です。
特別受益は相続トラブルの原因となりやすく、遺産分割協議や調停での解決が必要になることも多くあります。
証拠資料の準備が重要で、時効がないことにも注意が必要です。
特別受益に関する疑問や不安がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
-
成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などを理由に判断能力が不十分となった方々は、ご自身で契約を結ぶことや財産を管理することが難しく、ご自身に不利益な契約を騙されて締結してしまったり、財産管理を誤ってしまったりして、不利益を被るおそ […]

-
犯罪被害
損害賠償請求とは、相手方の「債務不履行」あるいは「不法行為」によって損害を受けてしまった場合に、金銭的な補償をしてもらうことのできる請求をいいます。「債務不履行」とは、相手方と契約関係にある場合で、相手方が契約に基づく債 […]

-
企業法務を弁護士に依...
「定期的に社内でコンプライアンスの研修を行いたいと考えているが、研修を指導できる人員がおらず困っている。」「民法改正に伴って取引に利用している契約書の改定を行いたいと考えているが、どの部分を変えればよいか分からず停滞して […]

-
交渉・契約
「民法の改正があったと聞いたが、利用している古い契約書を更新する必要があるだろうか。」「取引先から契約書の内容変更を打診された。当社にとっては不利となる可能性があるが、応じる必要があるだろうか。」契約や交渉について、こう […]

-
欠陥住宅
新築の住宅に雨漏りが生じたり、不自然な隙間が見つかったりして、欠陥住宅であることが判明した場合、一定の場合では法的な救済を得ることができます。見つかった欠陥をそのまま放置するのではなく、建築業者や不動産業者に報告すること […]

-
相続放棄とは?手続き...
相続の対象になる財産は、現金や不動産などのプラスの財産だけではありません。借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。しかしマイナスの財産が多い場合には、相続放棄という選択も可能です。この記事では、相続放棄の方法やそ […]

よく検索されるキーワード
弁護士紹介
昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
-
- 第二東京弁護士会(17922)
- 第二東京弁護士会裁判員センター
- 日弁連刑事弁護センター幹事
- 著書
-
- 裁判員裁判のいま(成文堂)
- 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
- 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
- 裁判員制度の10年(日本評論社)
事務所概要
| 名称 | フェアネス法律事務所 弁護士 牧野 茂 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル10階 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:050-3173-8287 / FAX:03-3500-5331 |
| 対応時間 | 平日:9:00~18:00 ※時間外も対応しております(要予約) |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※対応しております(要予約) |
| アクセス |
地下鉄銀座線虎ノ門駅下車(7番出口より徒歩1分) 丸ノ内線・日比谷線・千代田線 霞が関駅下車 A12出口より 徒歩3分 |