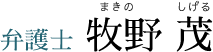寄与分と特別受益とは?その違いを詳しく解説
相続における寄与分と特別受益は、相続人間の公平な財産分配を実現するための重要な制度です。
相続人それぞれの被相続人への貢献度や、生前に受けた財産を適切に評価することで、納得のいく相続が可能となります。
本記事では、寄与分と特別受益の違いや具体例について解説します。
相続における寄与分と特別受益の違いとは?
相続における分配の公平性を守るため、寄与分と特別受益という2つの仕組みが設けられており、両者は相続財産の分け方を調整する重要な制度です。
寄与分は、被相続人の財産を増やすために尽くした相続人に対して認められる権利です。
反対に特別受益とは、故人が存命中に相続人へ渡した財産や学費などの援助を指します。
相続手続きでは、相続人それぞれの貢献度と、すでに受け取った財産の有無を確認し、その結果に基づいて、最終的な相続の配分額が決まっていくのです。
以下では、寄与分と特別受益について、具体的な内容をみていきましょう。
寄与分の考え方
寄与分は、民法904条の2が定める制度です。
寄与分が認められた相続人には、通常の相続分に加えて追加の配分が行われます。
その一方、他の相続人への配分額は少なくなります。
このような調整の仕組みによって、相続人一人ひとりの貢献度に応じた公平な財産分配が実現できるのです。
相続で認められる寄与行為とは?
相続における寄与分は、被相続人に対する具体的な貢献によって判断されます。
代表的な寄与行為は以下の5つに分類できます。
- 労務提供型
- 財産出資型
- 療養看護型
- 扶養型
- 財産管理型
それぞれの寄与行為の詳細な内容についてみていきましょう。
労務提供型の寄与行為
被相続人が営む事業への労働力の提供は、寄与分として評価されます。
農業や漁業などの家業、製造業や小売業の手伝い、医師や税理士などの専門職支援が対象です。
事業価値の向上に貢献した場合、寄与分が認定される可能性があります。
財産出資型の寄与行為
財産出資型の寄与分は、被相続人への金銭的支援などの財産上の給付が対象です。
事業資金の提供やリフォーム費用の負担など、相続人が金銭の贈与などを行い、被相続人の資産価値を高めた場合に認められます。
療養看護型の寄与行為
療養看護型の寄与分は、被相続人の介護や看病に従事した場合のことです。
専門の介護サービスを利用せず、相続人が直接介護することで費用が節約された場合に、相続財産の維持や増加が認められる場合に限り認められます。
扶養型の寄与行為
扶養型の寄与分は、被相続人の生活を経済的に支えたことで、財産が維持された場合に認定されます。
相続人が被相続人と同居して生活費を負担したり、日常的な世話をすることで生活費が節約できた場合が対象です。
財産管理型の寄与行為
財産管理型の寄与分は、被相続人の資産を適切に運用管理した場合に認定されます。
相続人が被相続人に代わって不動産管理や税金納付を行い、資産価値の維持向上に貢献した場合が対象です。
特別受益の考え方
特別受益制度は、民法903条1項に定められた制度です。
被相続人から生前贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合、その財産価値を相続分に含めて計算します。
これにより、相続人間の公平な財産分配が実現します。
特別受益の4つの具体例
代表的な特別受益の例は、以下の4種類です。
- 遺贈による財産
- 生前に贈与された財産
- 生命保険金と死亡退職金
- 借地権の譲渡や設定
これらの具体的な内容について順に説明していきます。
遺贈による財産
遺贈とは、被相続人が遺言で行う財産の無償譲渡です。
民法903条により、遺贈された財産はすべて特別受益として扱われ、相続分の計算に含まれます。
「相続させる」という遺言についても、同様の取り扱いとなります。
生前に贈与された財産
生前贈与のうち、特定の目的を持つものは特別受益として認定されます。
民法の定めでは、婚姻・養子縁組のための贈与や事業開業資金、学費など、生計の資本となる贈与が対象です。
結婚・養子縁組の際の贈与について
婚姻や養子縁組における贈与は、その性質により特別受益かどうかにより判断されます。
新生活のための持参金や支度金は特別受益の対象です。
一方で、結納金や挙式費用は、親の立場での社会的支出として扱われるため、対象外です。
生計の資本となる贈与について
たとえば学費の場合、特別受益に該当するかどうかの判断は、被相続人の状況に応じて行われます。
大学や留学などの教育費用は、被相続人の資産状況や社会的立場から見て、通常の扶養義務を超える支援である場合には特別受益となります。
一般的な教育費用は、扶養の範囲内として特別受益には含まれません。
生命保険金と死亡退職金について
生命保険金と死亡退職金は、基本的に特別受益の対象外です。
しかし、民法903条の趣旨に照らして、相続人間の不公平が著しいと判断される特別な事情がある場合には、例外的に特別受益として扱われます。
判断の際は、保険金や退職金の金額、特定の相続人への集中度、他の相続人との不公平さの程度が考慮されます。
このような調整により、相続人全員にとって公平な相続の実現が可能です。
借地権の譲渡や設定について
被相続人から相続人への生前の借地権譲渡や、相続人の建物建築時の借地権設定は、適切な対価が支払われていない場合に特別受益として扱われます。
ただし、借地権価格相当額や適正な権利金が支払われている場合は、経済的な対価が成立しているため、特別受益の対象とはなりません。
まとめ
相続における寄与分と特別受益は、相続人間の公平性を実現するための重要な制度です。
寄与分は被相続人への介護や事業支援などの貢献が評価され、特別受益は生前贈与や遺贈などの先払い財産が考慮されます。
寄与分や特別受益に関する判断は複雑なため、相続の手続きを進める際は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
-
再開発事業に関するト...
■再開発事業問題とは将来的に新たな街づくりを行う際、複数の土地をまとめて一体的に建て替えることを都市再開発といいます。再開発事業問題とは、こうした都市再開発に伴う古い土地(元の土地)に住まれている方への立ち退き料の支払い […]

-
賃貸物件で起きたトラ...
賃貸物件に関して、入居者同士のトラブルや、退居時の敷金返還や原状回復の問題、立ち退き問題、賃料増額問題など、さまざまなトラブルが起こる可能性があります。 特に退居する際の敷金返還と原状回復に関するトラブルは、多 […]

-
損害賠償として請求で...
事故によるケガや契約違反によって損害を被った際には損害賠償を請求できますが、具体的に請求できるものを把握している方は多くありません。この記事では、損害賠償として請求できるものや種類、計算方法について解説します。損害賠償の […]

-
賃料の減額交渉と減額...
賃貸物件の賃料が高額だと感じる場合、オーナーに対して減額交渉することが可能です。減額してほしい旨を相談するだけでなく、条件によっては法的に減額請求できる可能性もあります。この記事では、賃料の減額交渉と減額請求権を行使でき […]

-
法定相続人の範囲
■法定相続人とは法定相続人とは、亡くなられた方の相続される財産を包括承継することのできる法的な資格を持つ人のことをいいます。亡くなられた方の意思によって相続人を創造することができないため、法定相続人とされています。&nb […]

-
相続財産が不動産のみ...
相続財産(遺産)が土地や家屋といった不動産のみの場合、相続をするにあたり問題が生じることがあります。具体的には、どのように不動産を相続人間で分けるか、という問題がそれです。しかし、この問題に対する処方箋はいくつかあります […]

よく検索されるキーワード
弁護士紹介
昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
-
- 第二東京弁護士会(17922)
- 第二東京弁護士会裁判員センター
- 日弁連刑事弁護センター幹事
- 著書
-
- 裁判員裁判のいま(成文堂)
- 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
- 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
- 裁判員制度の10年(日本評論社)
事務所概要
| 名称 | フェアネス法律事務所 弁護士 牧野 茂 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル10階 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:050-3173-8287 / FAX:03-3500-5331 |
| 対応時間 | 平日:9:00~18:00 ※時間外も対応しております(要予約) |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※対応しております(要予約) |
| アクセス |
地下鉄銀座線虎ノ門駅下車(7番出口より徒歩1分) 丸ノ内線・日比谷線・千代田線 霞が関駅下車 A12出口より 徒歩3分 |