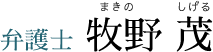受遺者とは何?相続の際に遺産分割協議に参加しなくてはいけないかについて解説
遺言書によって財産を受け取る権利を持つのが「受遺者」です。
遺産を受け取るひとは「特定受遺者」または「包括受遺者」のいずれかに分類されます。
両者の間では、遺産に関する法的な権利や責任の範囲が大きく違うので注意しましょう。
本記事では、受遺者についての簡単な知識から、特定受遺者・包括受遺者それぞれの権利、相続人との違いまでをわかりやすく解説します。
受遺者についての基礎知識
財産を託すために遺言書を作成する人物を遺贈者と呼び、遺言書によって財産を託す仕組みのことを遺贈と定めています。
遺贈を受け取る側には大きく分けて2つのタイプがあり、財産を受け取る人物は「特定受遺者」と「包括受遺者」のどちらかに該当するのが一般的です。
「特定受遺者」の権利と遺産分割協議への参加の要否
「特定受遺者」とは、遺言書の中で具体的な財産を受け取るよう指定された人物のことです。
たとえば、「東京都渋谷区の土地を山田一郎さんに譲る」といった明確な形で指定されています。
重要なポイントは、特定受遺者には借金などの負債を受け継ぐ義務がないことです。
遺産分割協議へは、参加しなくてもかまいません。
財産を受け取る権利は、受遺者自身の意思で辞退することが可能です。
辞退を希望する場合は、相続人か遺言執行者に対して意思表示を行うだけで手続きは終了となり、家庭裁判所への手続きも必要ありません。
「包括受遺者」の権利と遺産分割協議への参加の要否
包括受遺者は、遺言書によって財産を一括で受け取る立場にあります。
そのため、相続人と等しい権利を持ち、遺産の分割協議に参加することが求められます。
財産を受け取らない選択をする場合は、包括受遺者となったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所での手続きが必要です。
手続きの方法は相続放棄の場合と同様です。
遺産相続における包括受遺者は、4つの異なる種類があります。
遺産をすべて受け継ぐ「全部包括受遺者」
全部包括受遺者には、遺産の全てを受け取る権利が与えられています。
遺言書に基づいて財産全体が譲渡され、預貯金などの資産だけでなく、借金などの負債も全て引き継がなくてはいけません。
財産が一括して一人に引き継がれる仕組みのため、遺産分割協議の必要はありません。
遺産を一定割合で受け継ぐ「割合的包括受遺者」
割合的包括受遺者は、遺産の一定の割合を受け取るように遺言書で指定された人物です。
具体的には、「遺産の3割を山田花子さんへ」といった形で割合が明記され、預貯金などの資産も、借金などの負債も定められた割合に応じて引き継ぎます。
遺産の一部を受け取る権利があるため、遺産分割協議への参加が必要です。
特定財産を除いた残りを受け継ぐ「特定財産を除いた財産についての包括受遺者」
特定の財産を除いた残りの遺産全てを受け取る人物を指します。
たとえば「マンションは佐藤さんへ、その他の財産は鈴木さんへ」といった形で指定されます。
指定された特定の財産以外の全ての遺産を引き継ぐ立場となり、受遺者が1名の場合は遺産分割の話し合いは不要ですが、複数名いる場合は話し合いが必要です。
遺産の換金後に代金を受け継ぐ「清算型包括受遺者」
清算型包括受遺者とは、遺産を現金化した後の金額から指定された割合を受け取る人物のことです。
たとえば「土地を売却し、その売却代金の3分の1を田中さんへ」といった形で指定されており、遺産を換金した後の金額から、遺言書で定められた割合で受け取ります。
受遺者と法定相続人の権利や立場にはどのような違いがあるのか?
相続人と受遺者では、被相続人の財産を引き継ぐ際の法的な立場が異なるので注意しましょう。
民法第990条の定めにより、包括受遺者は相続人と等しい権利を持っていますが、法律上で定められた権利内容には違いがあります。
受遺者には代襲相続が認められない
相続人が亡くなった場合は代襲相続により、その権利を子や孫が引き継ぐことが可能です。
一方、受遺者が遺贈者よりも先に亡くなってしまった場合、遺贈を受ける権利は失効します。
このように、遺贈は相続と比べて権利の引き継ぎに制限が定められているのが特徴です。
相続放棄があっても受遺分は増加しない
遺贈による財産の取得は、遺言書に明確に記載された範囲に限定されています。
相続の場合、ある相続人が権利を放棄すると他の相続人の取り分が増えます。
しかし、受遺者は遺言書で指定された財産だけを取得し、それ以上の財産を受け取ることはできません。
仮にすべての相続人が相続を放棄したとしても、遺言書に示された以上の財産を受遺者が受け取ることはありません。
法人を含む団体も受遺者として指定できる
遺贈では、会社や団体を財産の受取人として指定することができます。
一方、相続人の範囲は民法によって厳密に決められているので注意が必要です。
相続人による遺贈への異議申し立ての可能性に注意
相続人には、遺贈の内容に対して法律で認められた2つの対抗手段があります。
1つ目は遺留分侵害額請求です。
兄弟姉妹を除く相続人には遺留分が定められており、遺贈により遺留分を下回った場合は不足分を請求できます。
2つ目は遺言無効の訴えです。
遺言の形式に不備がある場合や、遺言者の意思能力が不十分だった場合は、相続人が無効を訴えることができます。
多くの場合は当事者間の話し合いで解決しますが、調停や訴訟に発展することもあります。
遺言が無効と認められた場合、受遺者は遺産を受け継ぐことが不可能です。
まとめ
遺言書により財産を受け取る受遺者には、特定受遺者と包括受遺者の2つのタイプがあります。
特定受遺者は個別の財産を受け取り、遺産分割協議に参加しなくてもかまいません。
一方、包括受遺者は相続人に近い権利を持ち、全部・割合的・特定財産除外・清算型の4種類があります。
ただし、代襲相続が認められないなど、相続人とは異なる制限があります。
遺贈に関する権利関係は複雑なため、不安な点がある場合は弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
-
相続人の調査方法
■相続人の調査とは相続人の調査とは、相続が開始された際に、相続人が誰であるかを特定する調査のことをいいます。こうした調査が必要となるのは、相続をする際遺産分割協議を行うことが原因です。遺産の相続の仕方を話し合う遺産分割協 […]

-
遺産分割協議書を作成...
相続が発生すると、相続人の間で「遺産分割協議」という話し合いを行います。被相続人(亡くなられた方)が生前に遺言書を残していれば、その内容に従って遺産分割を行いますが、遺言書を残していない場合には、「遺産分割協議」において […]

-
再開発事業に関するト...
■再開発事業問題とは将来的に新たな街づくりを行う際、複数の土地をまとめて一体的に建て替えることを都市再開発といいます。再開発事業問題とは、こうした都市再開発に伴う古い土地(元の土地)に住まれている方への立ち退き料の支払い […]

-
コンプライアンス・危...
「社員のコンプライアンス意識向上を図るため、コンプライアンス教育を行いたいが、適切な方法が分からず実施できないままでいる。」「自社ではリスクマネジメントの一環として内部通報制度を制定しているが、十分に機能しているかどうか […]

-
賃貸物件で起きたトラ...
賃貸物件に関して、入居者同士のトラブルや、退居時の敷金返還や原状回復の問題、立ち退き問題、賃料増額問題など、さまざまなトラブルが起こる可能性があります。 特に退居する際の敷金返還と原状回復に関するトラブルは、多 […]

-
親権・監護権
「子どもがいる状況で離婚するが、親権者がどちらとなるかでもめている。やはり父親が親権者となるのは難しいのだろうか。」「協議離婚を検討しているが、親権者と子どもと暮らす親は別でも良いと聞いた。これは本当だろうか。」離婚を検 […]

よく検索されるキーワード
弁護士紹介
昭和25年12月5日生まれ。慶應大学法学部を卒業。第二東京弁護士会に所属。弁護士として、30年以上のキャリアを持つベテランの弁護士です。
市民生活の法律問題全般や企業法務を幅広く扱っています。
また、社会問題への参画として日弁連裁判員本部委員を努めるなど、裁判員制度の推進・改善を目指す活動にも貢献。市民の皆様が裁判員として効率的に仕事ができるよう、有志で裁判員経験者との交流団体である裁判員経験者ネットワークを設立し、共同代表世話人として2ヶ月に一度、交流会を開催するなど、積極的な活動を続けています。
裁判員経験者ネットワーク https://saibanin-keiken.net/
弁護士 牧野 茂
- 所属団体
-
- 第二東京弁護士会(17922)
- 第二東京弁護士会裁判員センター
- 日弁連刑事弁護センター幹事
- 著書
-
- 裁判員裁判のいま(成文堂)
- 取調べの録画ビデオ~その撮り方と証拠化~(成文堂)
- 「民事陪審は実現できる」(二弁フロンティア2020年1月2月論考)
- 裁判員制度の10年(日本評論社)
事務所概要
| 名称 | フェアネス法律事務所 弁護士 牧野 茂 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル10階 |
| 電話番号 / FAX番号 | TEL:050-3173-8287 / FAX:03-3500-5331 |
| 対応時間 | 平日:9:00~18:00 ※時間外も対応しております(要予約) |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※対応しております(要予約) |
| アクセス |
地下鉄銀座線虎ノ門駅下車(7番出口より徒歩1分) 丸ノ内線・日比谷線・千代田線 霞が関駅下車 A12出口より 徒歩3分 |